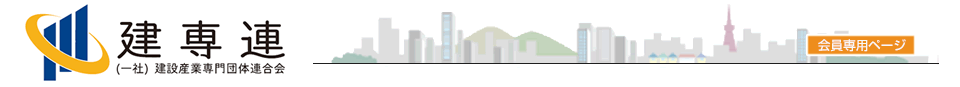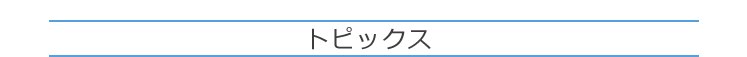
第1回 下請代金支払確保措置について - 勤労者退職金共済機構 副理事長 六波羅 昭
建設会社の倒産、整理が続出して下請代金の不払い事故が後を断たない。この問題に関しては、諸外国にくらべて日本の制度の不備が指摘されてきた。請負代金の保全について日本では、抵当権の設定、留置権、不動産工事の先取特権などの制度はあるが、元請でも使いにくく、まして発注者と直接契約関係がない下請では、これらはほとんど使われることがない。
フランスでは1975年の下請法により、(1)元請業者は発注者に対して下請業者を提示して承認を求める、(2)元請業者は下請業者の代金債権のために銀行保証を得る義務がある、(3)発注者に承認された下請業者は発注者が元請に対して負っている債務の限度内で発注者に下請代金を支払わせる権利を持つなどが制定された。
また、韓国では建設産業基本法、下請取引公正化法によって、一定の条件のもとで発注者が下請代金を直接下請業者に対して支払うことができ、さらに請負契約締結時に元請から下請に対して下請代金支払保証を提出し、下請は元請に契約履行保証を提出するという制度を持っている。 米国ではメカニクス・リーン法により、下請代金債権、資材供給代金債権の先取特権が確立している。同法が及ばない公共工事に関しては、ミラー法(1935年)により連邦の公共工事について契約履行保証(パフォーマンスボンド)及び下請等代金支払保証(ペイメントボンド)の提出を元請業者に義務付けた。ほとんどの州でも同趣旨の立法がなされ、現在は公共工事全般にこの制度が及んでいる。また、民間工事についても、発注者は、下請代金の二重払いを回避するためにペイメントボンドを利用するようだ。
それでは、日本のように法制度の不備が指摘される中でどのような措置が有効なのか。昨年来、法制審議会で担保・執行法制の見直しが議論され、先般、最終答申があった。この議論の過程で、留置権や不動産の先取特権などが抵当権執行に対し妨害的に主張されることが少なくないとの問題提起があり、さらに、金融機関サイドから、抵当物件を競売にかけても商事留置権があるために抵当権が無剰余になるケースがあるので、商事留置権については抵当権に対抗できないようにすべきという意見が提出され、中間とりまとめの段階では、商事留置権は不動産に成立しないとする改正方向が出ていたが、建設業関係団体の強い反対意見によって最終答申からは除かれた。こうした動きをみると、正当な建設工事代金の保全について行政あるいは法制関係者の理解が著しく不足していることがわかる。この問題をもっと広くいろいろな場で論議する必要がある。
昨年、国土交通省からは、公共工事について下請代金の不払いがあった時に、発注者が直接下請業者に工事代金を支払う仕組みが提案された。発注者と元請業者の工事請負契約において、発注者が元請代金を支払う時点で支払期限にある下請代金の不払いがあるときには発注者が元請代金の一部を直接下請業者に支払う旨の特約を付そうというものである。これについては、発注者にとって下請代金の支払状況確認など事務の煩雑さや、民間工事が対象にならないなどの問題が指摘された。
また、米国のような支払保証(ペイメントボンド)も検討されている。発注者の事務的煩雑さは解決でき、更生手続きや他の債権との優劣関係などの問題もなく、もっとも効果的な方策ではないかと思われるが、今のところビジネスとして成立するかどうか疑問視されている。現状のように代金不払い事故の損害は、下請業者が泣いて済んでしまえば発注者には問題がない。あえて保証料を払おうとはしないだろう。発注者、元請、下請それぞれが不払いリスクを分担する制度基盤がなければ支払保証のニーズが生まれない。米国ではメカニクス・リーン法とミラー法であり、フランス、韓国の発注者による下請代金直接支払い制度と保証の義務化がそれにあたる。
日本の場合、民間工事を含めて下請代金債権の保全措置(不動産の先取特権制度を下請負人にも認めるなど)の整備を図るべきであるが、法制化手続きに時間がかかるので、建設業界の総意があれば実施可能な公共工事下請代金の発注者直接支払い措置を緊急対応として先行的に講じ、これをベースに支払保証サービスを導入する方向が望ましい。